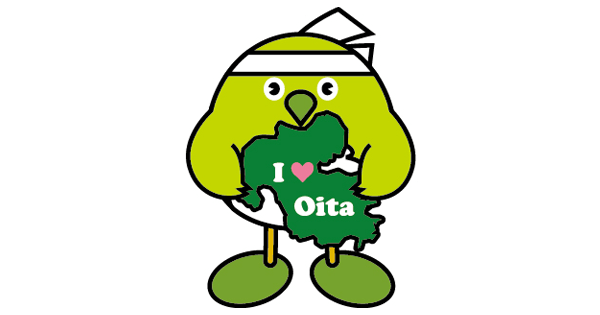<お祭り大好き>
町田の居酒屋「うらやましか」 旧暦の1月7日 豊後高田市の天念寺 修正鬼会は国東半島六郷満山に1000年以上前から伝わる伝統行事です。赤鬼(災払鬼)と黒鬼(荒鬼)が燃え盛る松明(たいまつ)を振り回し、僧侶と共に暴れ踊る演舞は最大の見どころで、各地からの参詣人で大賑わいします。五穀豊穣・無病息災を祈願するこの祭りは、国指定重要無形民俗文化財に指定されています。
2月 中津市北原の原田神社で行なわれる万年願(まんねんがん)で奉納される人形芝居が万年願・北原人形芝居です。鎌倉時代、北条時頼が諸国巡歴の途中この地で病に倒れた際に村人の看病で見事回復し、その祝いの席で始まったという伝承の歴史ある人形芝居です。踊りは狂言や浄瑠璃が取り入れられ、翁渡(おきなわたし)をはじめ全部で6幕が奉納されます。
疫病や災害などの様々な災いを払い鎮めるよう祈願する、宇佐神宮の鎮疫祭(御心経会)というお祭りは神仏習合の代表的な祭典です。古くは宇佐神宮と関係する寺院の僧侶が加わり、祭事のなかで般若心経を唱えることから「心経会(しんぎょうえ)」と呼ばれていました。宮司の祝詞奏上などの後、大幣(大きな御幣)を鳥居越しに奉納する「幣越神事」が始まります。この大幣がお守りとなるため、参拝者がその大幣の紙片や竹片を得ようと鳥居のところに殺到します。宇佐神宮鎮疫祭の大幣は日本最大級の御幣です。
杵築市の杵築散策とひいなめぐりでは、雛を「ひいな」と古語で呼び表し、江戸時代の古今雛や旧家で愛でてきたお雛様、杵築ならではの可愛らしい手作り雛などが華やかに彩ります。お雛様を展示する会場前では、目印の雪洞(ぼんぼり)や花餅(はなもち)が飾られ、城下町の雛祭りの雰囲気を華やかに盛り上げます。
7月 祇園信仰は全国に広まり、各地の夏祭りとして定着しているが、大分県でも県内の三大祇園祭りが有名です。
臼杵市の臼杵祇園まつりは、初日に行われる渡御(おわたり)では、先頭の槍振りと吹流しに続いて神輿と山車の行列が、「ミョウサヤ、ミョウサヤ」という掛け声とともに臼杵の城下町を練り歩きます。そして、祭り最終日の還御(おかえり)では「ミョウナンネ、ミョウナンネ」という掛け声で八坂神社へ戻っていきます。
日田市の日田祇園祭は絢爛豪華な山鉾が、祇園囃子の音色と共に町並みを巡行します。夜には提灯を飾り付けた優雅な「晩山」の巡行が行われ、祭りは一気に最高潮に達します。曳行で囃される祇園囃子は、俗曲、端唄をアレンジした独特のものです。
中津市の中津祇園は下祇園上祇園合わせて「祇園車」と呼ばれる踊り舞台のついた、漆塗りの華麗な13台の山車と2基の御神輿が中津の城下町を巡行し、祇園車の舞台では華麗な民舞などが奉納されます。
7月終わりの宇佐神宮の夏越大祭は氏子の無病息災や豊作を祈り、御祓会とも呼ばれ、宇佐の夏を彩る行事として親しまれている祭りです。初日の「お下り」では、神様を三基の神輿に載せて大鳥居から頓宮に向かい練り歩きます。昔は三基で先着争いをしたため「けんか祭り」と呼ばれていたが、今は先着争いは無いようです。祭り3日目の「お上り」は頓宮から上宮までを練り歩きます。3基の神輿を中心とした神輿行列は勇壮華麗な行列絵巻を見るようです。
8月 国東半島沿岸に浮かぶ美しい島・姫島の姫島盆踊りは「風流」の要素を取り入れた鎌倉時代の念仏踊りに由来するとされ、お盆に帰ってきた祖先の霊をなぐさめ、再び送るための行事です。最も知られている踊り、キツネ踊りは子供たちがキツネに扮して跳ね回る踊りです。顔を白く塗ってひげを描き、白ずくめの衣装に身を包んで白ギツネに扮した子どもたちが、キツネのしぐさを真似た踊りを披露します。
大分市の鶴崎踊はテンポの早い軽快な踊りの「左衛門(さえもん)」と、もう一つ、ゆっくりとした優雅でしなやかな手先や動きが特徴の踊り「猿丸太夫(さるまるだゆう)」は江戸時代に伊勢詣で行った人たちが「伊勢踊」を覚えて帰り、鶴崎で始めたのが始まりと言われています。
津久見扇子踊りは、戦国時代に戦没した勇士や農民の供養の願いをこめて、京舞いの流れを汲む扇子踊りが創られたと伝えられています。優雅・豊麗・哀歓をこめた扇子の流れが美しい踊りで津久見市を代表する郷土芸能として今日まで引き継がれている。
臼杵石仏火まつりは、磨崖仏の規模と数、彫刻の質の高さで日本を代表する石仏として国宝にも指定されている臼杵石仏群の、その参道などに約千本の松明をつける盛大な火祭りであり、石仏が松明やかがり火で照らし出される姿は荘厳です。昭和三十四年から地蔵祭りを発展させてはじめられたが、今では地元にも親しまれている行事で、当日は盆踊りなどのイベントも予定されています。
9月 柞原八幡宮の仲秋祭「浜の市」は、生石の浜へ三体のお神輿の渡御や神楽・民謡民舞・獅子舞・ベリーダンスの奉納、また、この祭りの間、出店も出てたいへん賑わいをみせます。江戸時代には、西日本の三大市のひとつに数えられ、府内城下町の最大のイベントでした。名物として、藩主の座布団を形どったとされる「しきし餅」や素朴な作りの「一文人形」があります。
10月 宇佐神宮の仲秋祭 蜷放生は宇佐神宮における最古の祭祀儀礼です。八幡大神様が御神輿に乗って、宇佐神宮から、和間地区の浜に建てられた浮殿という場所に神幸し、3日後の最終日に宇佐神宮へ御戻りになられます。この伝統的なこの行事の由来は、720年に起きた隼人の反乱にさかのぼります。反乱が起きた際、朝廷軍と共に八幡神が鎮圧して以降疫病や凶作など悪い事が続き、隼人の霊の祟りだと信じられていました。その霊を慰めるために仏教の殺生戒に基づいて生き物(蜷貝)を放って供養する放生会がはじまり、全国各地に広まったと云われています。歴史と伝統を今に伝える放生会は、神仏習合文化を如実に表している行事です。
仲秋の名月に合わせた城下町杵築観月祭」は、7千本の行燈と月明かりが武家屋敷や石畳を照らし、美しい満月と竹明かりが訪れる人々を幻想的な世界へと誘う。市民の工夫を凝らした光のオブジェなども見ることができ、どこからともなく琴や篠笛の音が聞こえてきます。武家屋敷では呈茶会が設けられ、琴の演奏会などが行われる。
国東市・岩倉神社のケベス祭は、宵祭りに異様な面をつけたケベスが主役となって活躍する火祭りの一種です。境内に設けられた燃え盛るシダの山に、木で作られた棒を持ってケベスが突入するのを、近くの海で禊ぎをした氏子が阻止するという、起源や由来が不明とされる祭りです。
11月 竹田市のたけた竹灯籠「竹楽」は、もともと里山保全百年計画としてスタートした催しです。日が暮れる頃、風情豊かな城下町に2万本の竹灯籠を灯し、幻想的な世界を演出します。城下町の数カ所では、軽音楽ライブが楽しめ、屋台村が出店し、郷土料理等を味わえます。
大野川合戦まつりは1586年12月12日に長宗我部・十河・仙石三大名の連合軍に大友軍を加えた六千余と島津軍二万五千が「戸次川原 」で激突した歴史的な出来事を後世に伝える祭りです。騎馬疾走や数々の郷土芸能、合戦さながらの「大野川合戦絵巻」が繰り広げられ、さらに歴史の波に翻弄され、戦場で敢え無く散ったつわものたちの霊を慰める花火が打ち上げられ夜空を焦がします。
大分県の花は 豊後梅
大分県の鳥は めじろ
大分県の木は 豊後梅
(大分県の公式ホームページ)